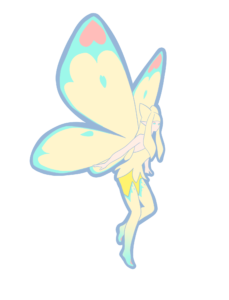仰々しいタイトルだが、要はただの読書感想文である。
ネタバレは極力控えている。
W・G・ゼーバルト “アウステルリッツ”
再度書いておくが幻想性の高さが比類ない。
時間に対する独特な概念の言及、蛾の話、好きな箇所を挙げるとキリがないが特段好きなのが中盤から舵を傾ける場面、リヴァプールである。
筆を取る精神状態でなくなる → “婦人待合室” → “私にとって世界は19世紀末で終わっていた” → ラジオ → プラハ
この流れが非常に美しい。事前情報なしでここまでを読むと流麗ではあるがどこかゆるんだ金糸のようなストーリーの紡ぎ方がされていたものが、この中盤の一合から糸がぴんと張ったようにひとつの道筋に収束するのが分かる。そして張った糸が緩むことは最後までない。
スケーリングする文章とでも言うべきか。描写の美しさについて特筆すべきは、終盤になればなるほど読者の没入感を利用した短文でも幻想性を損ねることなく、むしろ増幅する効果があるということだ。
ネタバレを控えているためにこれ以上のことは語れない。
クラウディオ・マグリス “ミクロコスミ”
アウステルリッツに引けを取らない幻想性の高い文章。しかし方向性が違う。そもそも”幻想性”とはなんぞやという話なのだが、今の私にはうまく表現することができない。どれだけ酔い痴れるかという感覚なのかもしれない。ただ私のイメージとしては、アウステルリッツの幻想性というのは蜃気楼のような霞のようなものであり、ミクロコスミの幻想性は綺羅びやかな万華鏡だ。
イタリアの北東部、境界都市トリエステの近辺を巡る旅の本だが、横道に逸れた寓話の数々には読み手の教養が求められる。外人には厳しいと誰が言ったのかは定かではないが、確かに西洋文明の歴史に詳しくないと厳しい場面が散見される。ヨブ記の主人公ヨブの息子の話が出てきたり、メデイアの闇の感情の話が延々と出てきたりとかだ。ただしそんなものはゆーてである。ユリシーズに比べれば求められる前提知識はそこまでない。
文章そのものの美しさはアウステルリッツに引けを取らないものの、大きな違いとしてミクロコスミには全体を通した明瞭なストーリーというものはない。異なる9つの土地を回っていく筆者の回想録に過ぎない……とは表現したいものの、それらを通した筆者の共通見解、1つの大きな思想があることは疑いようがない。しかしそれは明らかなものとして書かれず、水面下にこっそりあるだけだ。断片的な旅行記と捉えてもいいだろうし、その裏にある大きな根が何かを探してもよい。
ロベルト・ボラーニョ “2666”
2段組で900ページ弱。恐ろしく長い本であるがもともと5部別々の本にするはずのものを1冊にまとめたためこうなった、らしい。興味深い点がある。描写の精緻さはその紙面の長さからも類推できるほどではあるのだが、先の2冊と比較して”幻想性”という概念はまったくない。
これは2666の文章が先2つに対して劣っているというわけではない。ヨーロッパ及びメキシコにあたかも自身がいるような描写は見事の一言で、十分に物語に没入するだけの筆力はあるが、どうにも”酔い痴れる”といった感じではない。それはこちらのほうが描写が具体的であるからなのだろうか。よくわからない。
ストーリーとしては作家アルチンボルディを巡る広大な円環にまつわる話である。この膨大なページ数をもって風呂敷を綺麗にまとめ上げているのは素晴らしいの一言だが、それよりも印象に残った点がある。正しいセックスの描写をしているということだ。
性とは言うまでもない一大コンテンツを為す本能にまつわる要素だが、小説においても性をどう使うかというのは筆者の力量が試される領分である。そして性描写を適切に利用できている小説というのはそう多くはない。いや、小説のみならず娯楽作品であれば概ねそうだろう。ラッキースケベ満載でやることはやらない一線を超えないことを謎の美徳とする少年漫画や、ファストフードのように濫用する青年漫画や、その裏で密かにヤリまくりな女性向け漫画とか。小説においても童貞の大学生が書いたような村上春樹だったり、筒井康隆のひどさは今更挙げる必要もないだろう。
正しい性描写は2つの方向性があると考えている。1つは……そもそも一般的な異性愛を前提とするが、性の美しさを追求するのであれば”非対称性”に着目するということ、もう1つは性が世界観没入の後押しをすることだ。本書は後者をうまく利用している。それはすなわち、独特な貞操観念を通して”われわれの貞操観念とは違う”という異国情緒のエッセンスを入れることだ。
これは文字で見れば簡単だろうが、いい塩梅におとしこむのが結構難しい。普通でない貞操観念など、こと想像力豊かな日本人であればいくらでも膨らませられる領分だろうが、”セックスしないと出れない部屋”とか”地球上に男が自分しかいなくて種付けのために奔走する話”とか……いや、これらはあまりにも度が過ぎている例だが、それでも強弱を間違えるとそれは異国情緒ではなくただのファンタジーになってしまう。
性は味の素だ。入れるととりあえず旨味が出る感じのある魔法の粉だが、分量を間違えるとくどい味付けになり、ただただ無粋なだけになる。本著はただしくそれを使った。これは多くはない例になるだろう。
凪良ゆう “汝、星のごとく”
いきなり毛色が変わったものだが、話題に挙がったから読んだ。結論としては面白くない。いや、今は”Not for me”と言わないといけないんだっけか…。
小説で人間を出す場合、まず人間がちゃんと人間しているかという壁が最初にある。この壁を超えられていない筆頭例が筒井康隆であり、スーファミのRPGの村人ぐらい、あるいはマンボウぐらい脳が小さい存在を描写されても困るわけだが、本書についてはちゃんと人間は人間していた。
ただ単純に彼らの境遇と、ストーリーの紡ぎ方に抵抗があった。共感できないというかは、”特段目新しいものもないな……”とただ思った感じだ。Intentionalという言葉がもっとも当てはまるだろう。秒速5センチとはちょっと違うだろうが、そういった方向性の”あ~あ~。あるあるw”とでも言うべき既視感がどうしても拭えないような……まぁ娯楽作品としては大衆の同意を得られるものだろうが、明らかに未踏の何かを追ったような本ではない。としか言いようがない。
ちなみに本著は正しくセックスを書けていない。味の素いれちゃったねぇ……w
そんな書評書く必要ある?と思うかも知れない。次につながるのだ。
クラリッセ・リスペクトル “星の時”
謎の星かぶりである。先の本は主人公2人が互いの道しるべにはなろうが、決して交わらない星のような存在であることからそのタイトルになっているのだろうと解釈するが、一方で本著──ある少女の話をする少年の話はどうか。
小説で人物を出す時、どういった人物を出すかは筆者のさじ加減ひとつだ。”汝、星のごとく”はちゃんと人間を出してはいたが、彼らは私には合わなかった。いや、そもそも物語とは、どういった人物までを出すことができるのか?
その問いに答えてくれるのがこの本だ。100ページ程度の恐ろしく短い小説だが、インパクトは十分だろう。”ブラジル文学の秘宝”とのことだが、確かに他にはない独特の余韻がある。ただ少女の話をするだけではなく、おそらくは筆者の思考を体現した少年を介して語られるために、メタフィクション的な陳腐さは多少あれども、幻想性も十分にある(読みづらい箇所はそれなりにはあるが)。
で、”星の時”とはなんぞや?たったの100ページそこらで納得の話をよく書けるものだと感嘆した次第だ。
次回、
ミシェル・レリス “幻のアフリカ”
マルグリット・ユルスナール “黒の過程”
オルハン・パムク “雪”
ペーター・ハントケ “左ききの女”
アントニオ・タブッキ “レクイエム”
イタロ・カルヴィーノ “冬の夜ひとりの旅人が”
なんでまたこんな読むようになったのかよく分からないが、無敵時間のうちに読めるものは読んでおこうと思う。
中学~高校早期でこんだけ読んでたら文系に行ってただろうな……こんな面白い本どもがあるなんて、誰か教えてくれよ……。