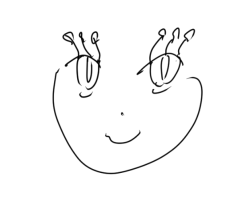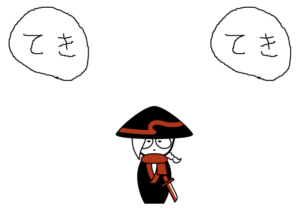初週が終わる。早々に見切りを着けたのは以前書いた通りだが、何をしていたのか。誰かの配信を見ながらゼーバルトの著作を読んでいた。
我らは何故文字を読み、音楽を聞き、絵画を見るのか。ゲームがそれらの複合芸術であるという話はさておき、身を震わすような大いなる体験を求めているのが1つの動機であることは疑いようもない。
そしてアウステルリッツ。凄まじい文章だ。某氏にはこれを小説であると紹介してしまったが、何か違う気がする。
ゼーバルトの作品は、小説とも、エッセイとも、旅行記とも、回想録ともつかない作品である。
W・G・ゼーバルト. アウステルリッツ (p.365). 株式会社 白水社. Kindle 版. (訳者あとがき)
私は海外小説が苦手である。レイモンド・チャンドラーを読みながら”かっるいわぁ……”と辟易し、ドストエフスキーを読みながら”おっもいわぁ……”と天を仰ぐ。当たり前のようにそれらを完読することはなかった。精々読み切れたのはハリー・ポッターや三体ぐらいのものだろう。技術書や専門書は容易に読み取れるのにも関わらず、何故海外小説が自分にとってこんなに厳しいのか。
それは作家の紡ぐ文章のテンポと、読者の思惑の猶予からなる日本文学独自のテンポ感に慣れているからなのだろうと思っている。日本文学は省略を重んじる。無論分厚い描写を織りなす作品もあるが、それでも海外小説と比べればまだ”遊び”がある。その遊びとは読者に思惑に没入させるような横道を提供する間が完備されていることであり、それこそが日本文学の美しさだと認識している。一方で海外文学は”一見すると不必要なほどに描写し尽くす”ように見えるのだ。
アウステルリッツも例外ではない。凄まじい描写が雪崩のようにページを開いた者に襲いかかる。なんせ改行がない。
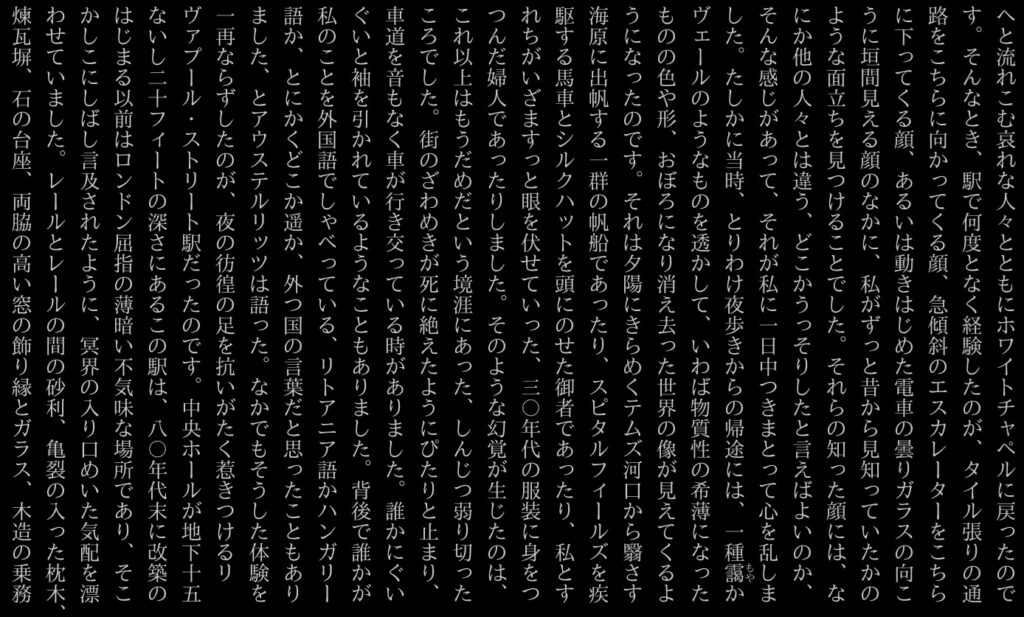
あーあーあー。きつい。きつすぎる。そして一文が長い。
その光は、埃の粒が一種きらきらと光っていると言えばよいのか、高い所ではたいそう明るいのに、下へ降りてくるうちにホールの壁と下方の空間に吸収されてしまうかのようで、暗がりをいっそう濃くするごとく、くろぐろとした筋となって、橅のつややかな幹やコンクリートのファサードをつたう雨水さながらに滑り落ちていくように見えました。W・G・ゼーバルト. アウステルリッツ (p.167). 株式会社 白水社. Kindle 版.
これだけでおおよそ160字である。
最近暇つぶしに渋で原神の二次創作小説を投下したら信じられないぐらい刺さらなくてビビったというのはただの余談だが、渋の二次創作はだいたいは推しカプがキャッキャウフフするのを楽しむのがメジャーなようで、ライトノベルよりも簡潔な文章が好まれるようだ。そのためか体感では5000字書けば中編で、1万字書けば長編に分類されかねるほどジャンキーに文を食する世界だ。そんな世界線で先述した文章を書くなら10数行で話を纏めなければならない。
まぁどちらの世界にも良さがあり、アウステルリッツはそういったジャンキーとは対極に位置する小説であって、海外小説の特徴に挙げた”イチからジュウまで書く”という性質をやはり持っている。問題なのは、それが全くもって不快ではないことだ。
これは訳者の巧みな仕事によるものでもあるのだろう。文章そのものの美しさ、こと日本語でも実感できる”文そのものの美学”が最初から最後まで一貫して見る者の脳裏に焼き付けられる。
徹底的な客観性と立ち上ってくる怨念のような主観性がふしぎに入り交じった、呪文のような魔力を持った文章がここにある。
W・G・ゼーバルト. アウステルリッツ (p.362). 株式会社 白水社. Kindle 版.(訳者あとがき)
卓越した音楽家の演奏の巧緻は、曲に依存せずとも知ることができる。ただ彼が鳴らす音一つ聞けば、その美しさを理解できる。その時に感ずるものと同等の経験がこの”文章”にはある。初めてロードバイクなどの良い自転車に乗った者は、その余りにも軽妙に運動するマシンに乗っ取られたように肉体の疲労を鑑みることなく進み続けると良く言われるが、自身でも経験がある。そのことを”自転車に乗ってるのではなく、乗らされている”と称するが、同様のことがこの本にも言える。”文を読むのではなく、読まされている”。それぐらいの没入感を海外小説で得たのは初めてのことであり、不思議な体験でもあった。そんなのが350ページ強も続く。
読後感を一言で言えば、”ジェットコースターに乗ってると思ったら急にレールが消失した”だろうか。それを喪失感と言うべきなのか爽快感と言うべきなのかは定かではない。しかし紛れもなく言えることは、久々にホンモノを見たということだけだ。川端康成の”小説の研究”に、書く者が必要とするものの1つに”感動”を挙げていた記憶があるが、それはまさしくこういった”ホンモノとどれだけ邂逅できるか”ということに他ならないだろう。
久々にいい気分になった。その気分のまま、ただ筆を取らされている。